抽象度とは?視点を変えるだけで人生が動き出す理由
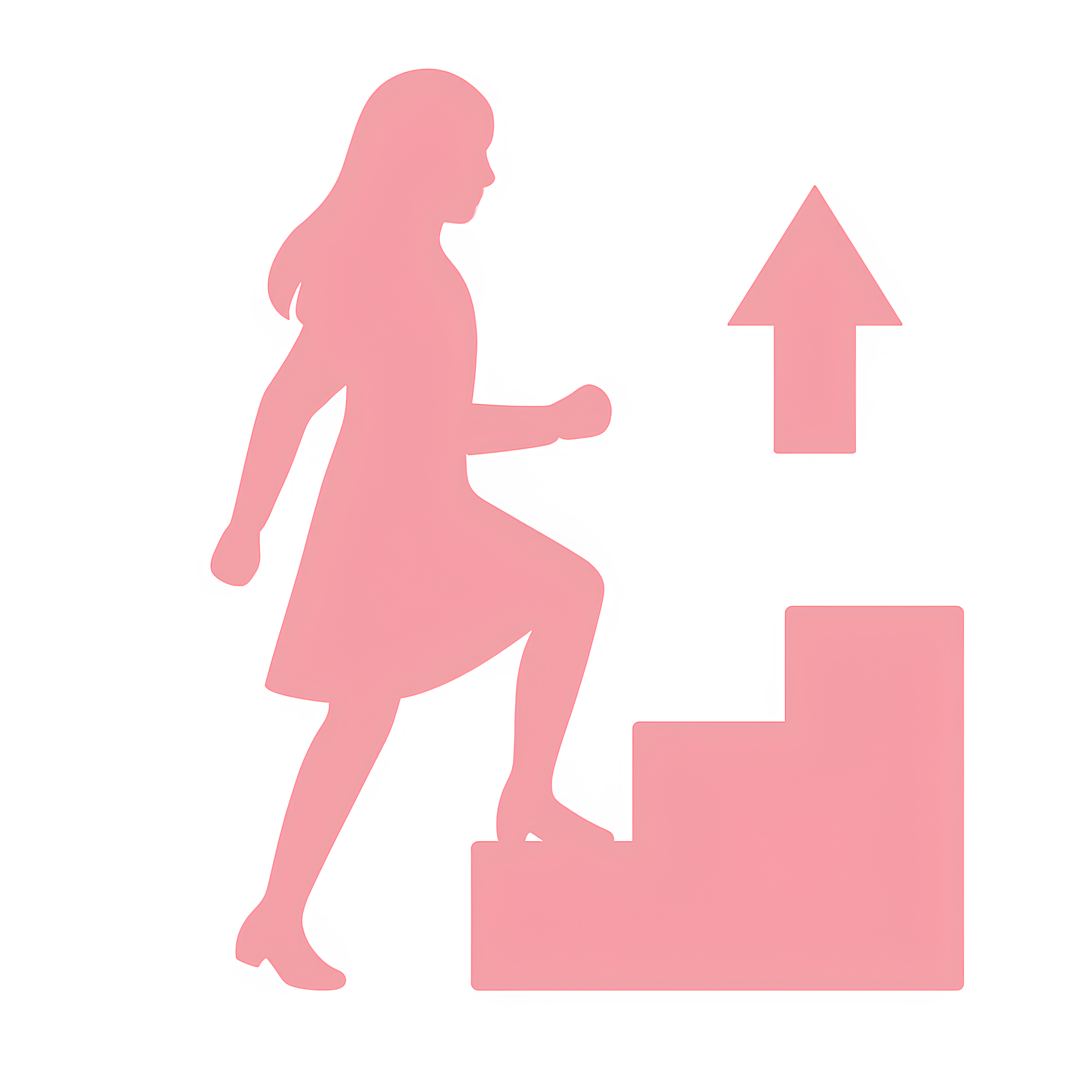
「毎日やることに追われて、何のために頑張っているのかわからなくなる」
「細かいことが気になって、本当に大切なことを見失ってしまう」
「もっと大きな視野で物事を見られたらいいのに」
こんな風に感じたことはありませんか?
実は、こうした悩みの多くは抽象度(視点の高さ)が固定されていることが原因かもしれません。
抽象度を自在に操れるようになると、悩みから抜け出すヒントが見つかり、なりたい自分への道筋が見えてきます。
この記事では、抽象度という概念と、それを日常で活かす方法をお伝えします。
抽象度とは何か
抽象度の定義
抽象度とは、概念を階層的に捉えるときの「情報量の大小」や「視点の高さ」を示す考え方です。
具体的な事実や細かな情報から離れて、より大きな枠組みや共通点に目を向けることで、物事を整理しやすくなります。
抽象度の高低
抽象度には「高い」と「低い」があり、それぞれに役割があります。
- 抽象度が高い:情報量が少なく、視点が広い(全体像、本質、目的)
- 抽象度が低い:情報量が多く、視点が狭い(具体的、詳細、行動)
どちらが良い・悪いというものではありません。大切なのは、状況に応じて使い分けられることなのです。
抽象度を理解するためのイメージ
カメラのズームに例えると
抽象度は、カメラのズーム機能に例えるとわかりやすいです。
ズームイン(抽象度が低い)
細部や具体的な対象にフォーカスしている状態です。
- 一本一本の木の葉が見える
- 具体的な行動が見える
- 細かい違いがわかる
ズームアウト(抽象度が高い)
全体像や背景を広く見渡している状態です。
- 森全体が見える
- 大きな目的や方向性がわかる
- 共通点が見える
どちらの視点も大切
ズームインしたままでは全体が見えず、ズームアウトしたままでは具体的な行動が見えません。
両方を自在に使えることが、柔軟な思考と豊かな人生につながります。
身近な例で理解する抽象度の階層
例1:大切なペットの「ココ」
ペットの名前から始めて、抽象度を上げていく例を見てみましょう。
最も具体的なレベル
「茶色のトイプードルのココ」
これは最も具体的で、情報量が多い状態です。一匹の個体を指しています。
少し抽象的なレベル
「犬」
トイプードル、柴犬、ゴールデンレトリバーなど、すべてを含みます。種としての共通点に注目しています。
さらに抽象的なレベル
「哺乳類」や「動物」
犬だけでなく、猫、馬、人間なども含む、より大きなカテゴリーです。
最も抽象的なレベル
「生物」「存在」
動物だけでなく植物なども含む、最も抽象的で情報量が少ない状態です。
例2:仕事のプレゼン資料作り
日常の仕事を例に、抽象度の階層を見てみましょう。
最も具体的なレベル
「今日の午後3時までにパワーポイントで10枚のスライドを作る」
すぐに行動できる、最も具体的な状態です。
少し抽象的なレベル
「プレゼン資料を作る」
パワーポイントかキーノートか、何枚かなどの詳細は含まれていません。
さらに抽象的なレベル
「プロジェクトを成功させる」
プレゼン資料作りは、その一部の手段として位置づけられます。
もっと抽象的なレベル
「仕事で成果を出す」「自分らしく豊かに生きる」
プロジェクトも仕事も、人生全体の一部として捉えられます。
抽象度の階層性
このように、抽象度を上げるとシンプルな概念へとまとまり、下げると具体性が増していきます。
この階層を自由に行き来できることが、豊かな思考の鍵になるのです。
抽象度が役立つ4つの場面
場面1:問題解決のとき
抽象度を下げると見えるもの
今日やるべき具体的な行動が見つかります。
たとえば「ダイエットしたい」という抽象的な目標があるとします。抽象度を下げると「今日は野菜を一品多く食べる」という具体的な行動に落とし込めます。
抽象度を上げると見えるもの
「なぜそれをやるのか」という目的や価値観を確認できます。
「野菜を食べる」→「健康になる」→「自分らしく生きる」という本質に気づけるのです。
場面2:人間関係で悩んでいるとき
抽象度が低いままだと
細かな違いにこだわってしまいます。
「あの人はこう言った」「私はこう思った」という具体的な出来事に囚われ、小さな違いが気になって関係がギクシャクしてしまうことがあります。
抽象度を高めると
共通の想いや目的が見えて、関係がスムーズになりやすくなります。
「お互いに大切にしていることは何か」という本質に目を向けられると、細かい違いよりも共通点が見えてきます。
場面3:目標を設定するとき
抽象度が低いままだと
「今やっていること」だけに囚われてしまいます。現状の延長線上の目標しか見えず、「もっと大きな可能性」に気づけません。
抽象度を高めると
現状を超えたゴールが見えてきます。
「本当はどうなりたいのか」という本質的な問いに答えられるようになり、現状の制約を超えた可能性が見えてくるのです。
場面4:悩みの中にいるとき
抽象度が低いままだと
目の前の問題に囚われてしまいます。「この問題をどう解決するか」だけを考え、視野が狭くなり、解決策が見つからないことがあります。
抽象度を高めると
違う角度から物事を見られるようになります。
「そもそもこの問題は重要なのか」「もっと大きな視点で見たら、どうか」と考えられるようになります。
抽象度を高める4つの方法
方法1:「なぜ?」を問い続ける
「なぜその行動をするのか?」と自分に問いかけると、より上位の目的にたどりつけます。
実践例:英語を勉強する理由
- 具体的な行動:「英語を勉強する」
- なぜ?:「海外で働きたいから」
- なぜ?:「自分の可能性を広げたいから」
- なぜ?:「自分らしい人生を生きたいから」
このように「なぜ?」を繰り返すことで、抽象度が上がり、本質的な目的が見えてきます。
方法2:「より大きな括り」を意識する
個別の事象を、より大きなカテゴリーでまとめることで、抽象度が上がります。
学びの階層で見てみると
- 具体的:英語の単語を覚える
- 少し抽象的:英語を勉強する
- さらに抽象的:語学を学ぶ
- もっと抽象的:学ぶこと全般
- 最も抽象的:自己成長、人生の豊かさ
方法3:時間軸を広げる
短期から長期へと時間軸を広げることで、自然に抽象度が上がります。
- 今日:今日やるべきこと
- 今週・今月:短期的な目標
- 今年:中期的な目標
- 3年後・10年後:長期的なビジョン
- 人生全体:人生全体の方向性
長いスパンで考えると、自然に抽象度が上がっていきます。
方法4:「もし〇〇だったら?」と問う
制約を外して考えることで、抽象度が上がります。
- 「もしお金が無限にあったら、何がしたいか?」
- 「もし時間が無限にあったら、何がしたいか?」
- 「もし失敗しないとわかっていたら、何がしたいか?」
こうした問いは、現状の制約から離れ、本質的な望みに気づかせてくれます。
抽象度を下げる3つの方法
抽象度を上げるだけでなく、下げることも同じくらい重要です。
方法1:「具体的には?」と問う
「具体的には何をするのか?」と自分に問いかけることで、抽象度が下がります。
実践例:幸せになりたい
- 抽象的:「幸せになりたい」
- 具体的には?:「家族と良い関係を築きたい」
- 具体的には?:「週に一度、家族と食事をする」
- 具体的には?:「今週の日曜日、18時に予約する」
方法2:5W1Hで考える
Who(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どのように)を明確にすることで、抽象度が下がります。
方法3:数字で表す
曖昧な表現を数字で表すことで、具体性が増します。
- 「痩せたい」→「3ヶ月で5kg痩せる」
- 「お金を貯めたい」→「1年で100万円貯める」
- 「もっと運動したい」→「週に3回、30分歩く」
抽象度のバランスが人生を豊かにする
高い抽象度の役割
- 目的や意義を見失わない
- なぜそれをやるのかが明確になる
- 大きな方向性がわかる
- 本質を見失わない
低い抽象度の役割
- 行動に具体性を持たせる
- 今日何をするかが明確になる
- すぐに行動できる
- 成果が測定できる
両者を行き来する柔軟さ
どちらか一方だけでは不十分です。
抽象度を上げて目的を確認し、抽象度を下げて具体的な行動を決める。この往復ができることが、ゴール達成や日常の充実に役立ちます。
抽象度を使いこなして、なりたい自分へ
抽象度とは、概念を階層的に捉えるときの視点の高さのことです。
高い抽象度は目的や価値観にアクセスする助けになり、低い抽象度は行動を明確にする助けになります。
「なぜ?」を問い続けること、大きな括りを意識すること、時間軸を広げること、制約を外して考えること。これらの方法で抽象度を高められます。
今、目の前のことに囚われて、大切なことを見失っていませんか?
まずは抽象度を上げて、「本当はどうなりたいのか」を確認してみてください。そして抽象度を下げて、「今日できる一歩は何か」を決めてください。
この往復ができるようになると、あなたの人生は、より自由で豊かなものになっていきます。